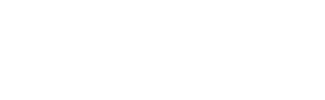定置網の変遷

明治34年制定の漁業法によって「定置網」という言葉が用いられるまで、富山湾沿岸では「台網」と呼ばれ、天正年間(1573から1592年)に始まったとされています。
網が画期的な発展を遂げたのは、明治40年、従来敷設・操業されていた数ケ統の台網を整理してまとめ、当時宮崎県で大漁が続いていた新型"日高式大敷網(三角網)"が導入されてからです。
その後、大正初年頃、阿尾(氷見)の上野八郎右衛門が日高式大敷網の欠点を改良し、網口など開口部を魚が逃げにくいように小さくした"上野式大謀網"を考案。(この上野式が今の「越中式落し網(大敷網)」の原型となっています。)
ついで、登り網を取り付けた「落し網」が大正後期から昭和初年頃に出現したと推測されます。
昭和40年代には「二重落し網」が考案され、それに伴い網の素材も改良が図られ、大規模な網の敷設が可能となりました。
三季の網から周年の網へ

氷見の大規模な定置網(大敷網)は、幾度かの変遷を経た後、昭和40年代頃から、各季節ごとに敷設していた"三季の網"から、周年性の網に変わりました。
現在では、"二重落し"を設けた網が広く普及し、以前のようにイワシをとる春網、マグロを主な対象とする夏網、ブリをとる秋網というふうに、季節ごとに網型や沈下する場所を変えることも見られなくなりました。
◆大敷網の仕組み
網は、氷見沖2から4km、水深40から70mのところに張られ、漁場までの時間は約20から30分、網を起こすのに30分から1時間程度かかります。
大敷網(二重落し網)の仕組みは、垣網・角戸網・登り網・身網の4部で構成されています。
- 垣網/魚を囲い網に誘導します。
- 角戸網/魚が最初に入りこむところで、回遊する溜り場、すなわち運動場。
- 登り網/一旦身網へ導かれた魚が、容易に網外へ出ないための網。
- 身網/魚をとり上げる網。
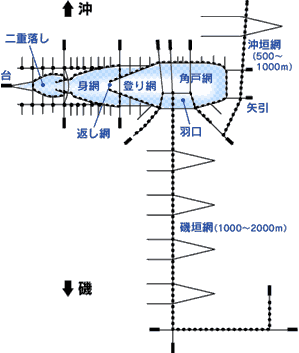
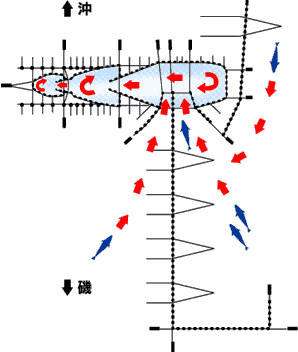
その他の漁法
氷見沖では、大敷網(大型定置網)や小網(小型定置網)のほかに、1.八艘張漁法 、 2.刺網漁法 、3.サヨリ船曳漁法などの漁法も操業されています。
- 八艘張漁法から海底に敷いた多角形の網の上で集魚灯をつけて魚を集め、8艘の漁船で網を引き上げる漁法。
主にカタクチイワシ・カマス・イカなどが対象です。 - 刺網漁法から魚介類の通り道に帯状の網をカーテンのように張り魚を捕獲します。
網を水面下で固定する"浮き刺し網"、海底に沈めて固定する"底刺網"、固定しない"流し網"があります。
氷見では、磯辺での磯刺(カレイ・クルマエビ)、沖合いの沖刺(ヒラメ・メバル・タラ等)が使い分けられています。 - サヨリ船曳漁法から2艘の漁船が魚群を抱えこむように投網し、並走して一定時間引き、袋網でサヨリを捕獲します。
- 定置網漁を遊覧船に乗って見学できます。
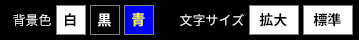

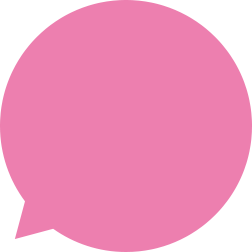 5分で分かる氷見のこと
5分で分かる氷見のこと